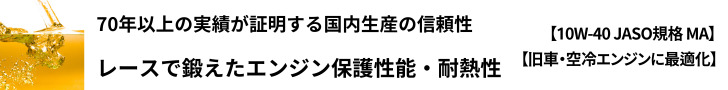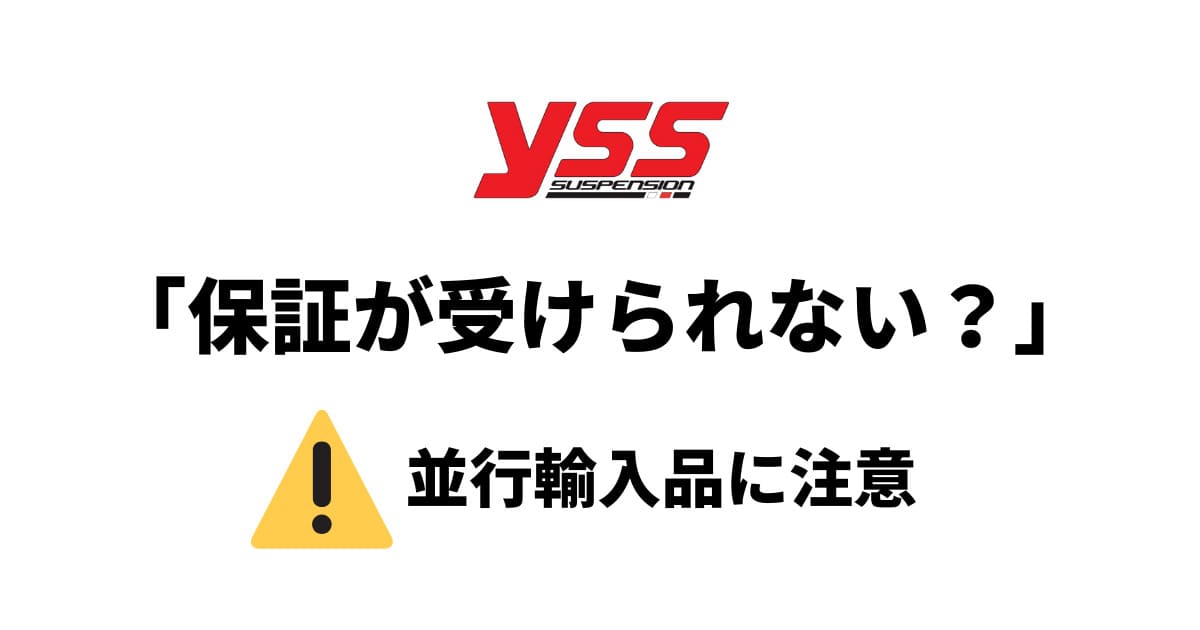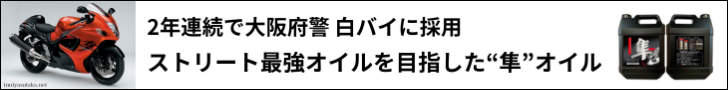「YSSのリアサスが気になるけど、耐久性や品質が心配・・・」
という方向けに過酷な耐久テストの結果と、なかなか一般には入手できない話を、証拠を提示しつつ、シェアします。
はじめに
通常より厳しい環境で使用したら?
YSSリアサスペンションを装着してトータル7年間(2018年〜2025年現在)、4本のテスト走行をおこないました。
製品モデルと距離
・CB125T JC06用 ME302:4年間 18,770km走行
・OD220-270P-04-16:3年間 16,518km走行
・OD220-315P-02-16:アドレスV125用 テスト中
かんたんに自己紹介させていただくと、筆者は2017年に有限会社ガレージ湘南とYSSと共同で、CB125T用 YSSリアサスペンションME302の開発に携わり、テストライダーを務めました。
(撮影・販売サイト製作・集客・販売戦略・プロモーション・コンテンツ制作をワンオペで手がけました)
私自身、この時に初めてYSS社のリアサスペンションを使う事になりましたので、耐久性が気になっていました。
YSSという名前は聞いたことがあるけど、くわしく知らない状況。
「タイ王国に本社があるらしい」
そのぐらいしか、知識がありませんでした。
ですので販売前のテストはもちろんのこと、販売を開始した後も、継続的に耐久テストをおこなっていました。
計5車種のリアサスをリリースしました
※2025年2月現在
・CB125T JC06用 ME302(2019年発売)
・VT250スパーダ用 ME302(2019年発売)
・CBR250RR MC22用 ME302(2020年発売)
・TZR50/TZR50R用 MB302(2024年発売)
・NSR250R MC18用 ME302(2024年発売)
→筆者検証の結果、2025年2月8日にMC16を対応モデルに追加し、YSS本社の公認を受ける。
これまで250名以上のお客さまに、YSSリアサスペンションを提供してきました。
購入者の方々からのフィードバックを蓄積し、私自身の4年 7年におよぶテストが終了したため、ようやく検証結果をお伝えできるようになりました。
(リアサス分解写真あり)
大事なこと
本題に入る前に、基本的な考え方を共有しておきます。
よく使われる言葉ですが「リアサスの寿命」って、すごくあいまいな表現です。
なので、まずは「具体的にどういう状態がリアサスの寿命なのか?」を明確に定義します。そうしないと、曲解や、誤解を生みかねないからです。
その上で、具体的な事例・解説をしていきます。
せっかく時間を使って記事を読むなら、肝心なポイントを見落したくないですよね。
そうならないために、熟慮した上で記事を構成しています。
バイク リアサスペンションの寿命って?
YSSの推奨は、フロントフォーク・リアサスペンションともに
(ストリート走行の場合)「10,000kmから20,000km走行、または2年に1度のオーバーホール(あるいは交換)」
YSSサスペンション取扱説明書より
とされています。
上記のメンテナンスサイクルは、オーリンズやWPサスペンションなど、ほかの社外サスペンションや、純正も基本的に同じです。
純正サスペンションだから特別、長持ちするというわけではないですし、「高額なサスペンションだから耐久性も高い」というわけではありません。
実際にはバイクや、ライダーの使用環境によって、かなり差があります。
それを踏まえた上で、「だいたい、これぐらいにはメンテナンスしたほうがいいよね」という目安が、上記のメンテナンスサイクルです。
レースで使用した場合の寿命
一般公道ではなく、ロードレースで使用した場合、
「20時間走行ごと or 1シーズン」
がオーバーホール(または交換)の推奨サイクルになっています。

リアサスペンションは、おおまかにスプリングと、ダンパー(減衰装置)の2つで構成されています。
ダンパーオイルの劣化

ダンパー(減衰装置)の中にはサスペンションオイル(ダンパーオイルともいいます)が入っていて、徐々に劣化していきます。
リアサスをメンテナンスしないまま、乗り続けると、こんな状態になります。

走行距離2万km以上、KTM390アドベンチャーのWPリアサスペンション
オーバーホールしないまま、放置して乗り続けると、最終的にオイルが灰色のペンキ(もしくは墨汁)みたいになる。

KTM300XC WPリアサスペンション 100時間使用後

かなり悲惨な状態です。
こうなると、オイルの粘度が失われて、水みたいにシャバシャバな状態になります。

オリフィス(写真左上 ダンパーオイルの流れをコントロールするための部品)が目づまりしている。
オイルシールなど内部部品の劣化
もちろんダンパーオイルの劣化だけでなく、内部のパーツも消耗します。

とくにオイルシールが劣化すると、ダンパーオイルが漏れてきます。
海外のライダーによると、ハイパープロ製のリアサスでオイル漏れが発生。メーカーに問い合わせたところ「20,000 kmごとにシール交換が必要」と回答があったそうです。
いっぽうで、4万km近く走行してもオイルが漏れないメーカーもあります。
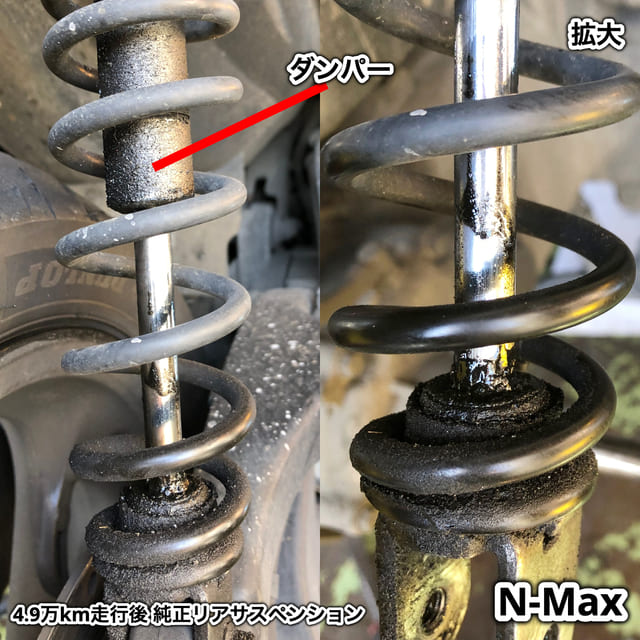
ボルトを締めた際のわずかな震動で、ダンパーオイルが鼻血のように垂れた純正リアサスペンション。
4.9万km走行していれば、無理もありません。
オイルが劣化すると、(エンジンオイルと同じように)粘度が低下して、シャバシャバになります。
ダンパーは路面の凹凸で、跳ね続けようとするスプリングの動きを抑えるのが役目ですが、ご覧のような状態だと、ダンパーが機能しなくなります。
・勢いよく縮む
・勢いよく伸びる
路面の凹凸に追従できない状態。
これがリアサスがへたった(抜けた)状態、リアサスの寿命です。
新品サスペンションを100%とした場合、徐々にサスペンションの性能が低下します。
新品時から徐々にサスペンションの役割である「路面追従性」が機能しなくなり、バイクの運動性能が低下していきます。
運動性能が低下するということは、
コーナー(カーブ)で曲がりにくくなったり、路面の凹凸でバイクが跳ねたり、物理的な変化が出てきます。
安全・スムーズに走れなくなってくるわけですから、心理的にも怖い思いをしたり、不安を感じたり、ストレスを感じたり、疲労感につながります。

減速帯を走行すると、サスペンションの劣化を感じやすいです。凹凸が連続して、車体がまるで、紙相撲のように跳ねるからです。
乗っている時に起きる症状の例
・コーナリング中、車体が跳ねて挙動が不安定になる
・コーナーリングで思うように曲がらず、膨らんでしまう
・路面の凹凸や、減速帯でバイクが跳ねてしまい、安心して走れない
・高速コーナーや高速道路の継ぎ目で車体がヨレる感じがする
・乗車時にシート高が下がりすぎる
・ダンパー調整(リバウンドアジャスター)してもほとんど効果が感じられない
・腰痛になる
中古車の場合、初心者ライダー、ベテランライダーに関係なく、購入時からダンパーが抜けていても
「こんなものかな」
と思って乗っている人が多いです。
見た目(外観)から、リアサスの寿命を判断しやすいのはオイル漏れです。
ただし、先ほど例に挙げたように、目に見える部分が大丈夫そうに見えても、目に見えない部分(内部パーツ)が劣化している場合もあるわけです。
見た目はあくまで判断基準の一つ、と考えたほうがいいでしょう。
オイル漏れしている場合や、ダンパーロッド(スピンドルロッド)に傷や錆がある場合、要メンテナンス時期と判断できます。
メンテナンスサイクルに関わらず、オイル漏れが発生したらオーバーホール or 交換になります。
もし、そのまま乗り続けると、乗り心地が悪くなったり、安全面で危険なほか、内部パーツの劣化が激しくなり、結果的にオーバーホール費用が高額になります。
中古品のリアサスは高い買い物
ここまで読んでくれた方は理解いただけたと思いますが、
外見(見た目)は良さそうでも、分解すると・・・・!? というのは、エンジンだけじゃなく、サスペンションも同じ。純正・社外品を問わず、「状態の良い中古品」は期待できない、という事です。
ちなみに海外のサスペンション メンテナンスショップも、私と同じことを注意喚起していました。
リアサスペンションのオーバーホール
一般的にオイルシールなどの交換や、ダンパーオイル交換をおこないます。
多くの方がご存じないようですが、注意すべき点もいくつかあります。
サスペンションの寿命まとめ
サスペンションは「スプリング」と「ダンパー」で構成されていて、ダンパーが先に寿命を迎えます(要メンテナンスの状態)。
自動車だとスプリングも縮むそうですがオートバイの場合、一般的には「サスの寿命=ダンパーや、オイルシールの寿命」と理解していいでしょう。
逮捕されないように注意
激安の中華製サスペンションや、有名ブランドの偽物は別体タンクが、ただの「飾り」の製品があります。
なんちゃって別体タンクです。
別体タンクに見える部品をくっつけているだけで、ダンパー内部は構造的につながっていない状態。見た目だけのハッタリ製品です。
(売れれば、何でもいいのでしょうか・・・)
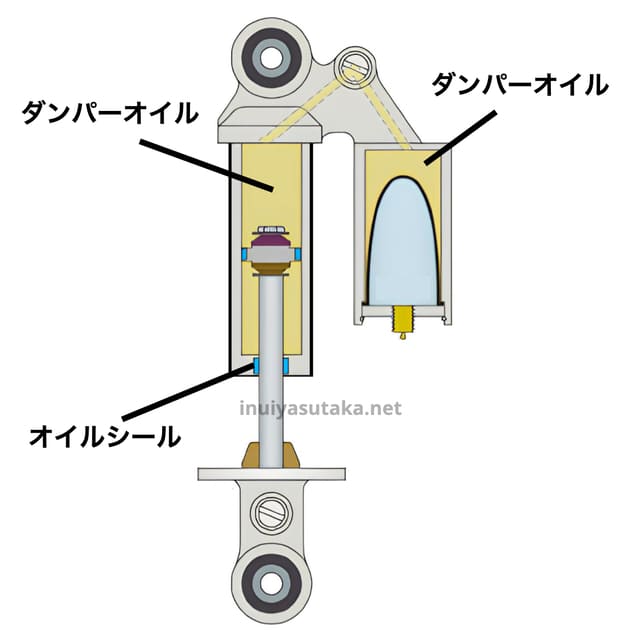
通常、リザーバータンク(別体タンク)と本体は、内部がつながっています
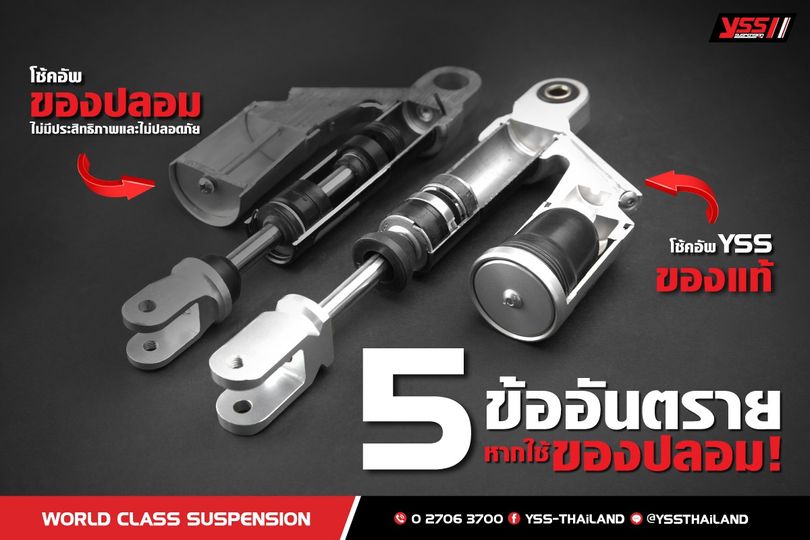
YSS公式の注意喚起
YSS以外の有名メーカーでも、こういったニセ物、粗悪品が出回っています。
「飾りでも、カッコいいから構わない」
という方もいるかもしれませんが、走行中にへし折れても不思議ではありません。
そもそもデタラメな物ですから、安全性はもちろん、製品として、まともな機能は全く期待できないわけです。
実験したサスペンション
ここからが本題。
テストをおこなったのはモデルME302、非分解式のリアサスペンション。イニシャル(プリロード)調整機能のみの、シンプルなエントリーモデル。
CB125T用イニシャル調整機能付きサスペンションとしては世界初です。

アルミボディの中では比較的、リーズナブルなME302シリーズ。
走行距離
1本目(試作品):3,576km
2本目:15,194km
仕様の異なるリアサスを2本テスト。
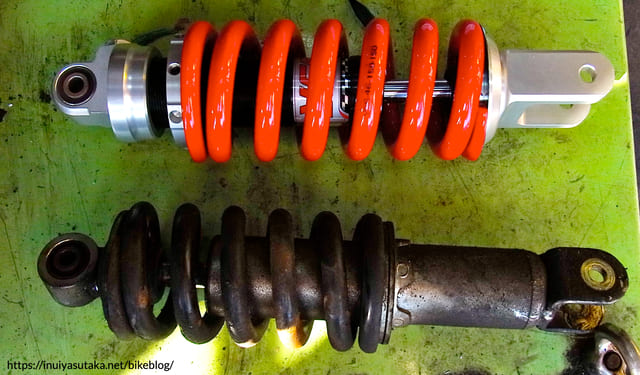
36,623km走行した純正サスペンションは、当然ながら抜けきっていた。
一度、新品純正に交換しているので劣化具合は、走行してはっきり分かるほど。
テストをおこなったバイク

HONDA CB125T改 2001年式(142cc化して軽二輪登録済み)
エンジン:空冷4サイクルOHC2バルブ2気筒
排気量:124cc
最高出力:15PS/11,000rpm
最大トルク:1.0kg-m/8,000rpm
車両重量:139kg
変速機:5速リターン
型式:CB125T 1
車体番号:JC06-1600001~
https://inuiyasutaka.net/bikeblog/series-spec/
過酷な条件
市街地、バイパス、高速道路、峠道、未舗装路など、公道で考えられるすべてのシチュエーションを、オールシーズン走行。
最低走行時間を2時間以上とし、とくに熱的にサスペンションに厳しい夏場は、あえて長時間の連続走行をおこなった。ダンパーオイルの油温をめいっぱい上昇させ、過酷な状況をつくることで、通常よりハードな負荷を与えるためだ。
多いときは、これを朝から夕方まで一週間、毎日おこなった。
加えて、10kg以上の重りを積んで走行したり、通常の走行なら避ける路面のギャップを、あえて通過するようにしていた。
(わざわざギャップのある箇所をめがけて走った)
サイトでくわしく話しているが、人間にとっても、この上なく過酷なテストだった。
リアサスペンションを分解
テストで使用した2本目(15,194km)のリアサスを、同製品の販売元である有限会社ガレージ湘南 日向社長に分解していただいた。
本来、非分解式のものを検証のために強引に分解している。
そのため金属片がついていたり、部品が一部、壊れているが、ご容赦願いたい。

メッキが施されたダンパー(減衰装置)のロッドはきれいなまま。オイル滲みもなかった。
あとでくわしくお伝えするが、劣悪な環境で放置していたにもかかわらず、少しもメッキにサビが発生していないのは優秀だと思う。

写真左の穴は窒素ガスを注入するところ。写真右は内側から撮影したものだ。

内部の壁面も大きな損傷は見られなかった。

写真はダンパーの中の部品を上からと、横から撮影したもの。
エンジンのシリンダー(筒)内をピストンが上下に往復するのと同じように、ダンパー内部でもピストンが動く。
ただ、エンジンとちがってダンパーのピストンには「オリフィス」と呼ばれる空洞がある(写真左)。空洞のなかをダンパーオイルがとおることで、ゆっくりと動くようになっている。

左が1本目に分解したサスペンションで、今回、分解したのは右側。
さきほど紹介したとおり、ストリート走行では10,000kmから20,000kmごと(または2年に1回)のオーバーホールが推奨メンテナンスサイクル。
そういった意味で15,194kmは、距離だけを考えると、まだ余裕がある。
ただし、通常よりも過酷な条件で使用したことを考慮すると、数字以上に負担がかかっている。それらを踏まえて言うと、ダンパーオイルの状態は妥当なところだった。
実際に走っている限りでは、体感レベルでリアサスのへたりを感じる事はなかった。
(高速道路で5速アクセル全開でコーナーリングできるほど)
YSSサスペンションの耐候性
これは意図せず、結果的に「耐候テスト」になってしまった。
1年6ヶ月もの間、屋外にバイクを放置した。
しかも、海まで徒歩10分のところに放置していたため、潮風や雨にさらされるというリアサスにとって劣悪な環境。(まったく磨いてない)

中華製フロントフォークや、各部のサビをご覧いただくと、どれほど厳しい環境かお分かりいただけると思う。

YSSスプリングは高品質なスチール素材「シリコンクロームが」使用され、パウダーコート(粉体塗装)が施されて、高耐久性が確保されている。
潮風や、風雨にさらされているだけあって、さすがにところどころ錆が発生していた。
ちなみに常時、海の近くに駐まっているバイクのリアサスをいくつも観察したが、これと同じような状態か、完全に錆びているものが多かった。
湘南エリアに住む、お客さんのバイク(ショーワ、カヤバ、オーリンズ、YSS、ナイトロンほか)を見ていても、だいたい、少なからず錆びている。
パウダーコートとは?
静電気の力を使って顔料を吹き付ける塗装のこと。バイクのフレームやホイル、身近なところでは自転車や洗濯機、ガードレールや信号機など、建築や工業用途でひろく使用されている。
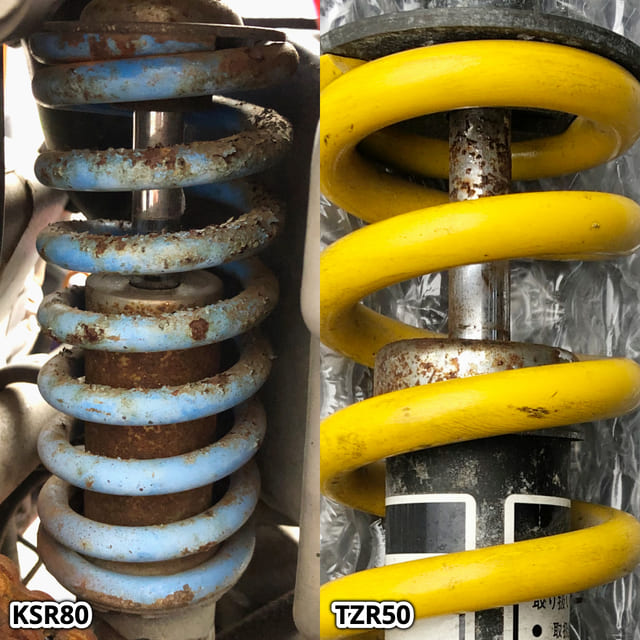
雨ざらしにされていたであろう湘南のKSR80はサビが酷く、朽ちかけている。
TZR50はヤフオクで落としたものだが、ダンパーロッドにサビが発生している。
保管状況が異なるので単純比較はできないものの、常時、海の近くに駐まっているバイクのリアサスがKSRに近い状態のものが多い事を考慮すると、YSSスプリングの耐久性は純正リアサスと同等以上だと思う。
筆者と同じような劣悪な環境で放置しないかぎり、そう簡単に錆びることはないはずだ。

通常、フロントフォークにも、リアサスのダンパーロッドの表面にも、サスペンションオイルが付着している。
ところが、前出の中華製フロントフォーク(写真)は激しく錆びているのに対して、分解したYSS製ダンパーロッドのメッキは少しも錆びていなかった。
この差はメッキの質によるところが大きいと考えられる。
筆者は純正・YSS以外の社外サスペンションの両方を含めて、(執筆時点で)90台分以上のサスペンションを観察しています。
その前提でいうと、
YSSのメッキ(ハードクロームメッキ)はオーリンズや、純正リアサスのメッキと比較しても、引けをとらないと実感しています。
スプリングの寿命
厳密にはダンパーだけではなく、スプリングも縮むと言われています(自動車で10万km走行した場合)。
ただし、今回取り外したスプリングは、1ミリも縮んでおらず、出荷状態と同じ長さのままでした。
【検証結果2】YSS 低価格なスクーター用リアサス
「マジかよ・・・」
スクーター用のリアサスペンションを使って、検証をおこないました。

製品モデル:OD220-270P-04-16 チッ素ガス入りダブルチューブ式
適合車種:スーパーDio/SR/ZX (AF27/28)
実売価格はおよそ5千円台。YSSのなかでは、かなり低価格帯の製品です。

取り付けた車両は、タイカワサキのLEO120。流用での使用です。
(レオはツインショックなので、Dio用を2本装着しました)
リアサス流用の注意点、問題点については、すでに以下の記事で解説したので、くわしくは話しませんが、
要点は以下のとおり。
1,車重が全然ちがう
Dio 車重 68kg
レオ 車重 97kg
車重が30kg近くも違えば、バネレート(ばねの硬さ)もダンパーの利きも、おおきく異なります。
2,巡航速度の差が2倍以上
Dio 原付 法定速度 30km/h
レオ 原付2種 60km/h
少なくとも、2倍以上も巡航速度が違います。
つまり、もともとレオで使用するには、柔らかすぎるわけです。
走行環境
冒頭で「リアサスの寿命は走行する環境によって異なる」とお伝えしました。
今回の走行テストでは、ダートを含むオフロードのほか、

真夏の峠道での連続走行、比較的、路面状況のわるい舗装路を日常的に走行。
かなり劣悪な環境で使用しています。
(メーカーの想定しうる使用環境を超えてると思います)
スクーター用 激安サスペンションの寿命
「公道で適合車種に取り付けて使用した場合、少なくとも15,000km以上は十分、使える」
これが結論です。
レオの場合、使用距離1.5万kmで気温が高い日は、ダンパーの利きが弱くなるのを実感しました。
使用距離1.1万km時点(3月)では、それほど気にならなかったんですけどね。
気温が高くなると、法定速度でゆっくり走っている時はあまり気になりませんが、ちょっとペースを上げて走行したとき、路面のギャップでフワフワするようになりました。
(さきほどお伝えしたとおり、ダンパーが寿命を迎えています)
繰り返しになりますが、そもそも取り付けた車両の重量が29kgも重たいわけですから、適合車種に取り付けて使用した場合は、それほど気にならないと思います。
なので低く見積もって15,000km以上としました。
実際にはケース・バイ・ケースですが、20,000km前後まで使えると思います。
ちなみに、流用して劣悪な環境で使用しても、使用距離16,518km時点でオイル漏れは一切、ありません。
2025年8月、新たにアドレスV125G用をテスト中です。
事例1:約4万km走行後、性能テストで新品同様だった
海外の事例ですが、アドベンチャーバイク(ヤマハ)で、1年で4万km近く走行したライダーがいます。

カザフスタンや中国、インドなど、中には道路と呼べない道を走行したYSSサスペンション(MG506)をYSSで性能評価テスト。

ほこりっぽい過酷な環境を走行したにも関わらず、オイルが漏れることなく、新品同様だったそうです。
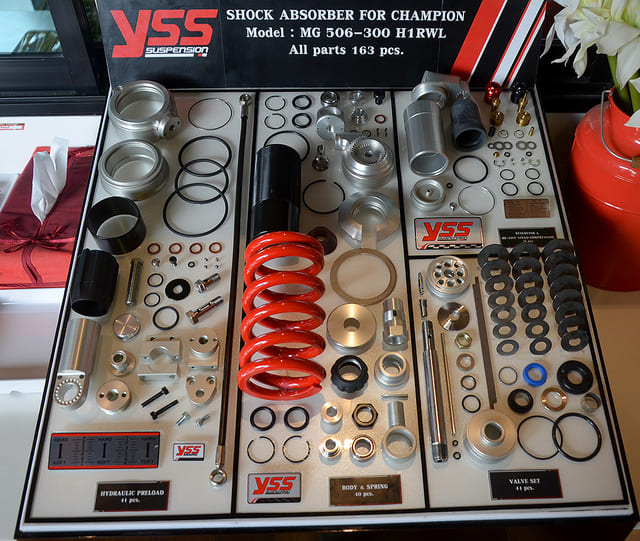
「ダンパーオイルは透明で、163個の部品を検査した結果、わずかな摩耗も確認できず、再び組み立てて、際装着できる」
かなり興味深い結果です。
ちなみに、ESAサスペンションを装着したBMW 1200GSAや、WPサスペンションを装着したKTM DR650と比較して、乗り心地・マシンの挙動において、YSSサスペンションがそれらを上回っていた、とコメントしていました。
メーカーの対応
同オーナーはハイパープロ(オランダ)のサスペンションを使用していた。
2万km走行して、オイル漏れが発生。
メーカーに問い合わせたところ、「2万kmごとにオイルシールを交換してください」と言われたそうです。
一般的なメーカーの意見としては、「それぐらい距離走ってるなら、まぁ漏れるよね。漏れたら交換したらいいんじゃない?」といった感じ。
この対応が良い悪いの話ではなく、プロの方々に言わせると本来、そういう認識のようです。
たとえば、20万km走行したエンジンからオイル漏れするようになっても、そんなに騒がないですね。それだけ走れば無理もないというか。
YSS メーカー推奨
ストリート走行
10,000kmから20,000kmごと(または2年に1回)のオーバーホール or 交換
事例2:さらに過酷な環境の使用実績
日本であまり知られていない、YSSの海外レース実績を紹介します。
ハーレーダビッドソン バガーレースでタイトル獲得
2022年12月、タイの「チャーン・インターナショナルサーキット」で開催されたハーレーダビッドソンのタイムアタックレース。
バイクの総重量は350kg。

新製品の倒立フロントフォークキットのほか、ステアリングダンパーと、リアサスペンションを装着したマシンは、ツーリングクラスで優勝(総合3位)


YSSは4輪のサスペンションも設計・開発していて、「世界一過酷なモータースポーツ」といわれるダカール・ラリーのマシンにも採用されています。
ダカールラリー 9,000km超を完走

サウジアラビアの砂漠の真ん中で丸 14 日間続くダカールラリー。
YSSレーサーの2名は、合計タイム60時間39分32秒、世界45人中14位で2023年のレースを完走しました。
事例3:世界選手権でファクトリーチームが採用
YSSのメイン市場であるヨーロッパでは、レーシングマシンにYSSサスペンションが採用され、数々のシリーズチャンピオン獲得や、勝利に貢献しています。
オーリンズからYSSへ

バーニーレーシングチーム スーパースポーツ世界選手権(WSSP)ヤリ・モンテッラ選手
スーパーバイク世界選手権(WSBK)で優勝実績を持つ名門チーム バーニー・レーシングチームが、2024年シーズンからスーパースポーツ世界選手権(WSSP)でYSSサスペンションに変更。
(2023年シーズンまでオーリンズを採用していました)

モンテッラ選手はシーズン終盤までチャンピオン争いを展開。
表彰台獲得数14回(優勝7回、2位4回、3位3回)、ポールポジション3回、シーズンランキング3位という好成績を残しました。
MVアグスタ 4レース連続表彰台
おなじくスーパースポーツ世界選手権(WSSP)で、MVアグスタのファクトリーチーム(ワークスチーム)「MV AGUSTA REPARTO CORSE」がYSSサスペンションを採用。


マルセル・シュロッター選手は開幕戦から4戦連続で表彰台を獲得し、シーズンランキング5位になりました。
WSSP300で4年連続タイトル獲得
スーパースポーツ300世界選手権(WSSP300)では、YSSサスペンションのサポートライダーが4年連続タイトル獲得。
ジェフリー・バイス選手(自身2度目のタイトル獲得)

アルヴァロ・ディアス選手 2022年
エイドリアン・フエルタス選手 2021年
ジェフリー・バイス選手 2020年
2024年はわずかに届かず、ロリス・ベネマン選手はシーズンランキング2位。
チームメイト ミルコ・ゲンナイ選手の活躍もあり、MTM KAWASAKI は5度目のチーム優勝を果たしました。
世界各国の選手権でチャンピオンを獲得
日本に全日本ロードレース選手権があるように、世界各国に国内最高峰のロードレース選手権が存在します。
MotoGPや、スーパーバイク世界選手権のライダーを数多く輩出しているスペインや、イタリアのほか、ニュージーランド、フランスにおいて、YSSは複数のカテゴリーでタイトルを獲得しています。

ブロンコス・レーシングチーム ロレンツォ・ザネッティ選手は、WSBK(スーパーバイク世界選手権)DUCATIのテストライダーを務めている。
2023年 CIV イタリアロードレース選手権 SBKクラスでシリーズチャンピオンとなった。

バーニー・レーシングチームのミケーレ・ピッロ選手は、MotoGP DUCATIの開発ライダー。
CIV SBKクラス 2015、2017、2018、2019、2021、2022、2024年シリーズチャンピオン。
ドゥカティ テストライダー2人の評価
2023年 YSS本社の広報資料によると、
「ミケーレ・ピッロ選手、ロレンツォ・ザネッティ選手ともにYSS製サスペンションを高く評価した」
とのコメントがありました。
まぁ、語らずとも2人のレース結果が証明していますが、MotoGP、WSBKそれぞれのテストライダーの評価は興味深い。
事例4:ドイツのクラシック バイクレース
オッシャースレーベン2023。
日本国内メーカー、ドゥカティ、ラベルダ、ビモータ、モトリーニ、トライアンフ、MVアグスタなど、1970年代から2000年ぐらいまでの旧車が参加するイベント。
参加車両を見ると、かなりの割合でYSSサスペンションユーザーがいる事がわかります。
多すぎて全部は紹介しきれないので、一部を紹介します。



以上YouTube オッシャースレーベン2023より引用
事例5:日本でYSSがオーリンズと同数
2025年6月20日、金曜日の午後。
筆者が筑波サーキットに足を運んだときの話。
MFJカップ JP250の車検が始まる直前、ならんで待っているエントリーマシンを1台ずつチェックしました。
数は20から21台。
そのうち5台は、YSSやオーリンズ以外、もしくはメーカー不明でした。
残り15、6台のマシンは、オーリンズとYSSが同数で横並び。念のため3回、数え直しましたが、結果は同じ。
数え間違いではなかったようです。
MFJ公式情報によると、エントリー数は30〜32台(そのうち何台が実際に車検を受けたかは不明)なので、筆者が目撃したのはそのうちの21、2台という事になります。
残り約10台はどのメーカーを使用しているか不明ですが、YSS勢が筆者が思ってた以上に多かったのはまぎれもない事実です。

JP250 第2戦 筑波で優勝した小室旭選手のKTM RC390
RRSは、YSSのプロレーサー向け レーシングリアサスペンション。
前出のスーパースポーツ世界選手権や、世界各国のロードレース選手権でおなじ製品が使用されています。
小室選手以外の筆者が目撃したマシンにも、レーシングサスペンションが装着されていました。
(プロ志向のクラスだけあって、ストリート向けを装着してるマシンは見当たりませんでした。当然ですが)

同じく小室選手のRC390。
YSSのレース用パーツ フロントフォークカートリッジキットが装着されていました。
レースによってレギュレーションが異なりますが、日本を含め、多くの場合、フロントフォーク自体の交換は認められておらず、内部パーツの交換のみ、認められているようです。
レーシングリアサスペンション同様、フロントフォークカートリッジキットも世界選手権や、タイトルを獲得した海外のロードレース選手権で装着されています。
(フロントに関しては今回、時間的にチェックする余裕がありませんでした)


世界各国のレース情報については、以下のブログで紹介しています。
YSSの世界シェア(市場占有率)
インドネシア、フィリピン、ベトナム、シンガポール、香港、韓国を含むASEANの市場では、当社はナンバーワンです。日本に関して言えば、当社は現在第2位です。
ヨーロッパはスクーターとオートバイの2つの市場に分かれています。
スクーターでは5年連続シェアNo.1を誇ります。現在、当社はドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、フランスでナンバーワンです。
YSSサスペンション 最高経営責任者ピニョ氏 2020年インタビューより
YSS VS オーリンズ 【検証】オーリンズ最強説は本当か? サスペンションのえらび方
事例6:オフロードでタイトル獲得

サイドカーを含め、オフロードレースでも数々のタイトルを獲得しています。
YSSサスペンションの硬さ・乗り心地
筆者はCB125Tに新品の純正リアサスペンションを装着して、走ったことがある。

抜けきった純正サスから新品に交換すると、しばらくは気持ちよく走れるが、15,000km走ったぐらいから顕著に柔らかく感じるようになった。
(軽二輪登録して、高速道路を走るため、より実感する)
20,000kmに達する頃には、交換前の純正サスと同じく、ダンパーが抜けた状態になった。
CB125Tの純正リアサスはもともとの設計が柔らかすぎると思うが、体重50kg未満の筆者が乗って、この有様。
だからYSSのCB125T用リアサスは純正と比較して、スプリング・ダンパーともに硬めの方向に設計してある。
(ストリート走行の場合)「10,000kmから20,000km走行、または2年に1度のオーバーホール(あるいは交換)」
YSSサスペンション取扱説明書より
メーカー推奨できっちりメンテナンスする人は少数派だと思われるため、
「ダンパーが劣化しても、しばらく乗り続けられる」といった事を想定して、ストリート走行で問題ない範囲での硬さにしている。
(すべてのYSSサスペンションが同じかどうかまでは分からないが、私たちがリリースした製品に関しては上記のとおり)
硬さ・乗り心地は簡単じゃない
乗り心地や、硬さの話は、食べ物の「おいしい」「まずい」みたいに、感覚的な話で終わりがちです。
1,ライダーの感覚、フィーリング
2,感じたことに対する解釈、評価
3,動作理論など、物理を理解した上での評価
「走った時のフィーリング」については、ライダー自身が感じたことなので、第三者が否定することはできません。
ただし、「2」の解釈や、その結果、導き出される評価については、間違っていることが多いです。
正しい評価をするためには、「3」の基本的な知識・経験が必要だからです。
エンジンでも、キャブレターでも、よくトンデモ理論や、珍回答が出てくるのは、基本的な仕組みや、動作理論を理解していないからです。
・タイヤが摩耗している
・空気圧不足
・(リンク式サスペンションの場合)リンクが固着
基本的な整備ができていない場合や、取り付けや、セッティングに問題のある場合も少なくありません。
にもかかわらず、自分の考えが正しいと思い込んだり、詳細な背景がわからないまま、安易に他人の情報を鵜呑みにするのは危険だと思います。
MotoGP(世界最高峰の2輪ロードレース選手権)のトップライダーでさえ、良くて「2」どまり。
実際にワークスチームのサスペンションメカニックをしていた方に聞いたり、メーカーの開発ライダーいわく、「3」ができるライダーはほぼ、いないそうです。
だからライダーの感覚的な話、漠然とした雲を掴むような話を、メカニックが聞いて、マシンの状態や、動作の状態を想像しながら、状況を分析するわけです。
その上で、ようやくセッティングすることができます。
・・・けっこう、深い部分がありますよね。
乗り心地はライダーの乗り方によって変わる
たとえば筆者の場合、凹凸の激しい路面を通過する時は腰を浮かせます。
ふだんはステップに荷重をかけて乗っていて、「シートにどっしり体重をあずけて座る」ということは通常、しないです。
その前提でいうと、筆者にとっての「乗り心地」は、たとえば必要な時に、必要なタイミングで、必要なぶんストロークしているかどうか。
硬さ過ぎて全然、ストロークしなかったり、ストロークするスピードが急すぎたり、遅すぎたり、無駄にストローク量が多いと、乗り心地が悪いわけです。
自動車のようにシートに座りっぱなしで、凹凸のある路面でもフワフワした乗り心地・・・
そういったフィーリングをバイクに求めていないんですね。
(自動車でたとえると、フィット・デミオ・スイフトよりも、クラシックミニ(ローバーミニ)のフィーリングのほうが好きだったりします)
もちろん、人によって乗り方はちがいますし、アメリカンタイプや、スクーターなどはポジション的に、シートに体重をあずけるようになっています。
これらを踏まえた上で、自分なりの「乗り心地」を定義しないと、情報に振り回されると思います。
YSS日本仕様の特徴
耐久性におおきく影響する話。
同じモデルのYSS製品でも、日本市場向けは、「オイルシール」がヨーロッパ市場向けと異なります。
オイルシールの注意点
巷では「低フリクション」(低抵抗)をうたったオイルシールが、もてはやされがちです。
しかし、ものごとは表裏一体で、メリットの裏返しはそのまま、デメリットになります。
たとえば、純正サスペンションに多く採用されるショーワの場合、オイル漏れ=クレームになりますから、フリクションロスを多少、犠牲にしてでも、シール性を高めているそうです。
オーリンズなど、低フリクションシールを使用した場合、動作性能には優れるものの、シール性や耐久面で劣ります。
それでも、頻繁に分解整備をおこなう競技用車両なら問題ありません。
ところが公道用バイクに低フリクションシールを使用した場合、バイクメーカーの推奨メンテナンスサイクル前に、シール劣化が原因で、オイル漏れが発生することがあります。
基本は純正品、社外品ならariete(アリート)を推奨いたします。
※オイルシールの考え方は、リアサスペンションも同様です。YSSの場合、日本向け製品はシール性を高めています。
国民性といいますか、日本人がオイル漏れに対して、敏感なための配慮だそうです。
オーリンズに関しては、オーバーホールから戻ってきてすぐ、またオイル漏れ・・・
というのを目撃したことがあります。
レースでオーリンズ製サスペンションを使っていた方に聞くと、今も昔も、漏れる(漏れやすい)のは事実なようです。
純正がフニャフニャになる理由
「公道を走るライダーは一般的によく動くサスペンションを好む傾向がある」
という統計があるそうです。
ですので日本車(国内向け)の場合、想定標準体重60kgから80kgぐらいの人が乗って比較的、よく動くように設計されています。
ある意味、柔らかい仕様といえます。
ただし、走行距離が伸びてダンパーが劣化すると、もともと柔らかいため、より顕著にリアサスの劣化を感じる事になります。
世の中、メンテナンスサイクルきっちりで、リアサス交換したり、オーバーホールする人は少ないですからね。
この点を考慮して、私たちが開発・販売しているYSSサスペンションについては、あえてバネレート(バネの硬さ)を高くしたり、ダンパーの利きを強めにしています。
装着後、最初は硬く感じるかもしれませんが、走行距離が伸びれば、ほど良くなる設計です。
これだと、純正とちがって、長く乗り続けられますからね。
まとめると・・・
・バイクがきちんと整備された状態
・リアサスの取り付けが適切で、セッティングも適切
・自分のコンフォートゾーンが切り替わり、サスの初期なじみが終わるぐらいの距離を走行する
少なくとも、これらを踏まえてはじめて、的確な判断・評価ができる状態になります。
非常に多いプリロード調整の誤解
筆者はYSSサスペンションに限らず、ウェブ上に存在する世界中のレビューに目を通しています。
適切にセッティングされていないと思われるケースや、あきらかに解釈・評価が間違っていると思われるレビューも、よく目の当たりにします。
たとえば、完全にダンパーが抜けた純正サスペンションを交換した直後は、「硬く」感じるのは当然ですし、
乗り心地と離れますが、プリロード(イニシャル)調整についても、多くの方が誤解して、まちがった評価をされています。
例:(ネジ式)プリロード調整が固い
リアサスペンションは、取り外した状態 or タイヤを浮かせて調整するのが基本です。
YSSに限らず、純正リアサスのプリロード調整も、サービスマニュアルに同様の注意書きがしてあります。
つまり、リアサスを装着して、タイヤを浮かせない状態で「プリロード調整が固い」「回らない」のは、設計者側からするとごく当たり前、という話になります。
設計意図と異なる使い方をすれば、不都合が生じるのは当然です。
新品なのにオイル漏れする2つの理由
1つは勘違い。
ダンパーを組み立てる際に使用するグリスが付着したものを「オイル漏れ」と思い込む人がいるようです。
(誤情報を配信したり、間違いをきちんと正さないユーチューバーもいます)
オイル漏れに関しては、以下の記事でくわしく解説しています。
リアサスペンションの寿命と交換時期
2つ目の理由は、並行輸入品を取り付けて、トラブルになるケースが多いようです。
原因について、下記の記事で解説しています。
大きすぎるリアサス流用の危険性
「自分のバイクには製品ラインナップがないから、他車種のものを流用しよう」
と考えている人がいるかもしれません。
もし流用した場合、どんな隠れたリスクがあるのか?、トラブル事例を紹介してます。
まちがった情報が表示されるAI
インターネットは手軽に情報を発信・受信できる反面、まちがった情報を信じるリスクもあります。
(オイルの記事にも書きましたが、有名バイクメディアも結構、まちがいが散見されます)
最近、とくに多いのがAIによる「まとめ情報」です。高確率で誤った情報が表示されます。
結論に飛びつかず、「なぜなのか?」根拠となる情報源をご自分でよく確認したほうがいいと思います。
ちなみに、
本記事を含め、YSSサスペンション耐久テスト結果を、わたしたちが各ネット媒体で発信するようになって、YSS製品を扱う業者さんが急に「高耐久性」をPRするようになりました。
今までそんなことサイトに書いてなかったのにね笑
あと、古い情報ではなく、アップデートされた新しい情報をチェックすることも大事です。
利用者のレビュー
筆者は直接、購入者の方とやりとりして意見や、感想を聞いています。
また、国内外のショッピングサイト、SNSを含め、あらゆるレビューに目を通しています。
もちろん否定的な意見や、レビューも見受けられます。
しかし、ほとんどのケースでは
- 正規品 or 並行輸入品(入手経路)
- 取り付けたバイクの状態(改造の有無、整備状態)
- 取り付けをおこなった人の作業レベル
- 操作やセッティングが適切だったか
- どういう使い方で、何キロ走行したか
これらの情報が不明確です。
なので、的を射た意見かどうか、言い分に妥当性があるかどうか、判断しかねると感じています。
事実、リアサスに限らず、操作方法や、取り付け作業をミスしたにもかかわらず、「製品のせいだ」と思い込んでいるケースが多々、あるからです。
断片的な情報、一部だけを切り取った情報を鵜呑みにするのは、けっこう危険かなと思います。
車種専用で、用途に合った正規品のサスペンションを正しく取り付け、適切な調整がおこなわれているかぎり、「社外品だから寿命が短い」ということはない、と考えていいです。
YSSサスペンションの欠陥率
ガレージ湘南では2019年にYSSサスペンションと共同開発・販売して以降、250本以上のYSSリアサスペンションを販売してきました。
欠陥や返品交換はないのか?
耐久性とあわせて気にされるお客さまのために、当店の事例をお知らせします。
結論から言うと、交換依頼は3件ありました。
1,お客さま自身の取り扱いミス(誤って窒素ガスを抜いた)
2,バイクのフレーム精度が原因で取り付け困難(その後、無事に解決)
3,「取り付けたリアサスが破損したので交換してほしい」との申し出があったが、ひとまず交換用のリアサスを発送したら、そのまま音信不通になった
3は通常、適切な使用では起こり得ない壊れかたでした。余談ですが破損したリアサスはYSSが測定器にかけるため、どのように力が加わったのか、判るようになっています。
※虚偽申告をすると詐欺罪(刑法第246条)に問われます
以上、サスペンション自体に欠陥があった件数はゼロです。
当店では上記以外の車種や、製品モデルも販売していますので、いずれも含めての話です。
出典:YSSサスペンションの欠陥率は?|YSS 正規販売店 ガレージ湘南
以下はガレージ湘南でリリースした製品、交換したYSSリアサスのレビュー。
お客さまから頂戴した内容をそのまま、掲載しています。
サスペンションのえらび方については、以下の記事でくわしく解説しています。