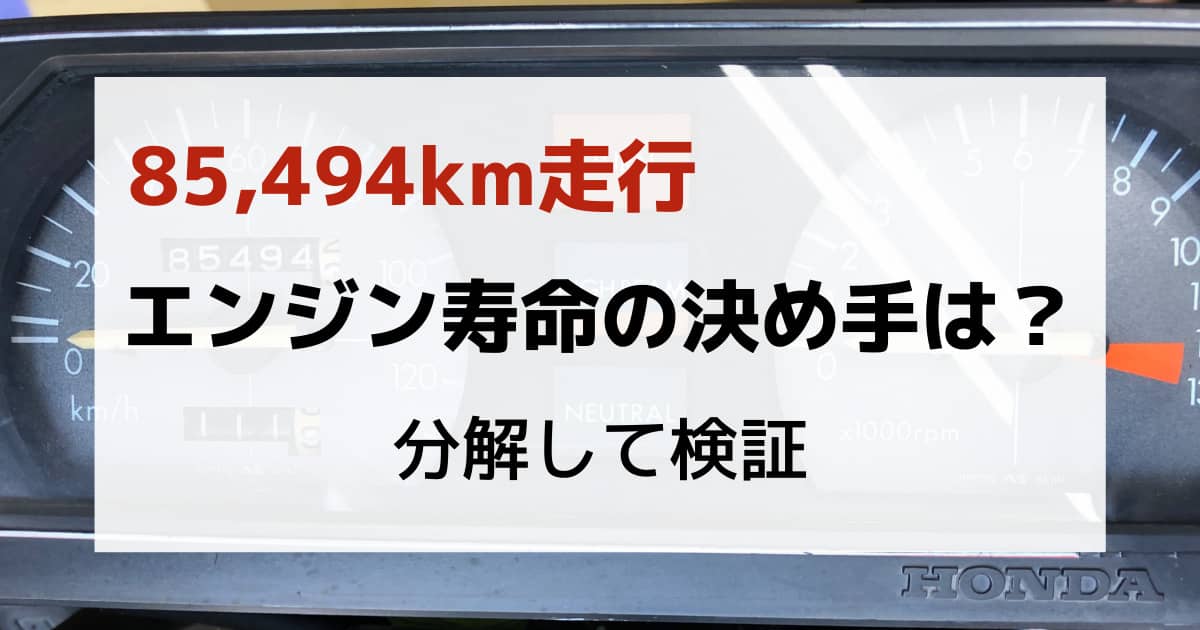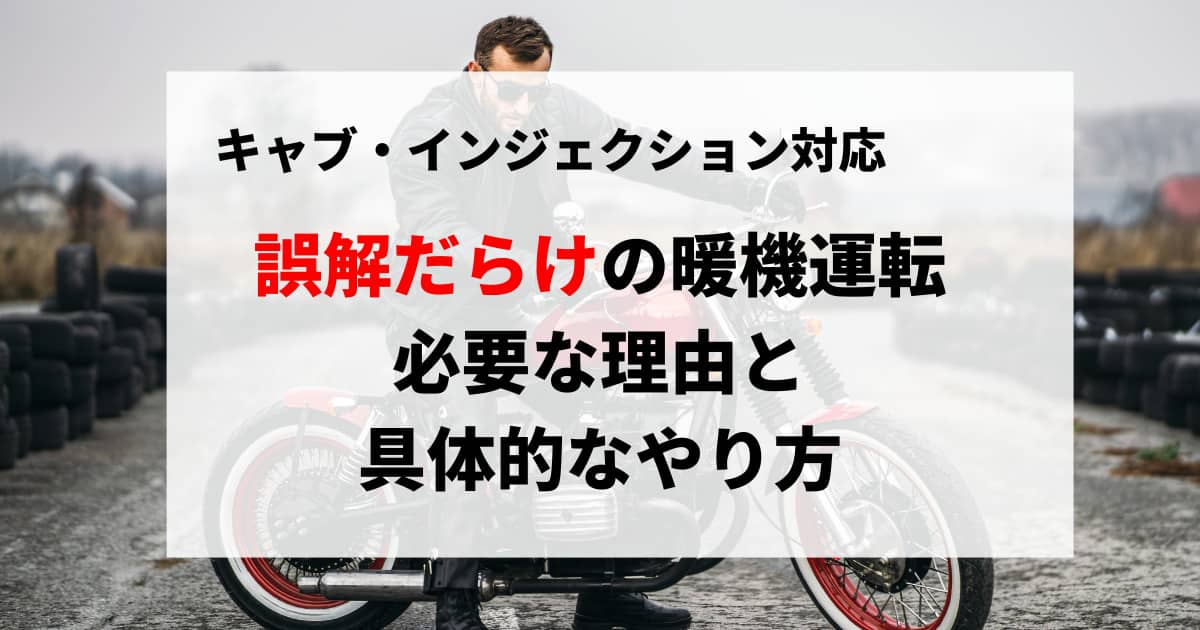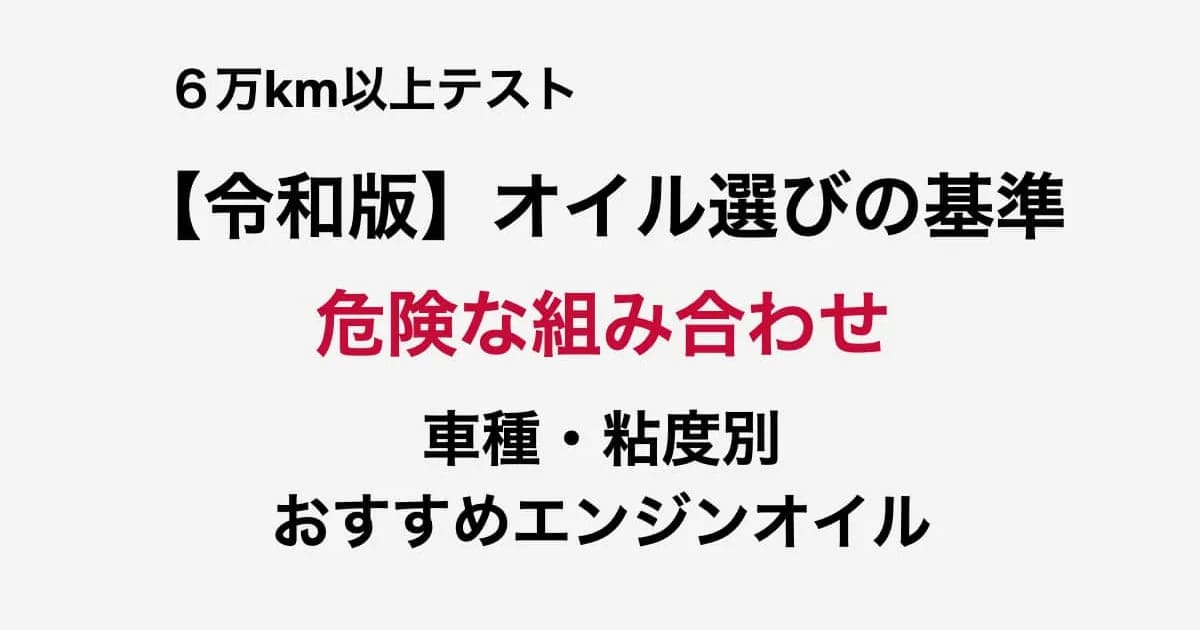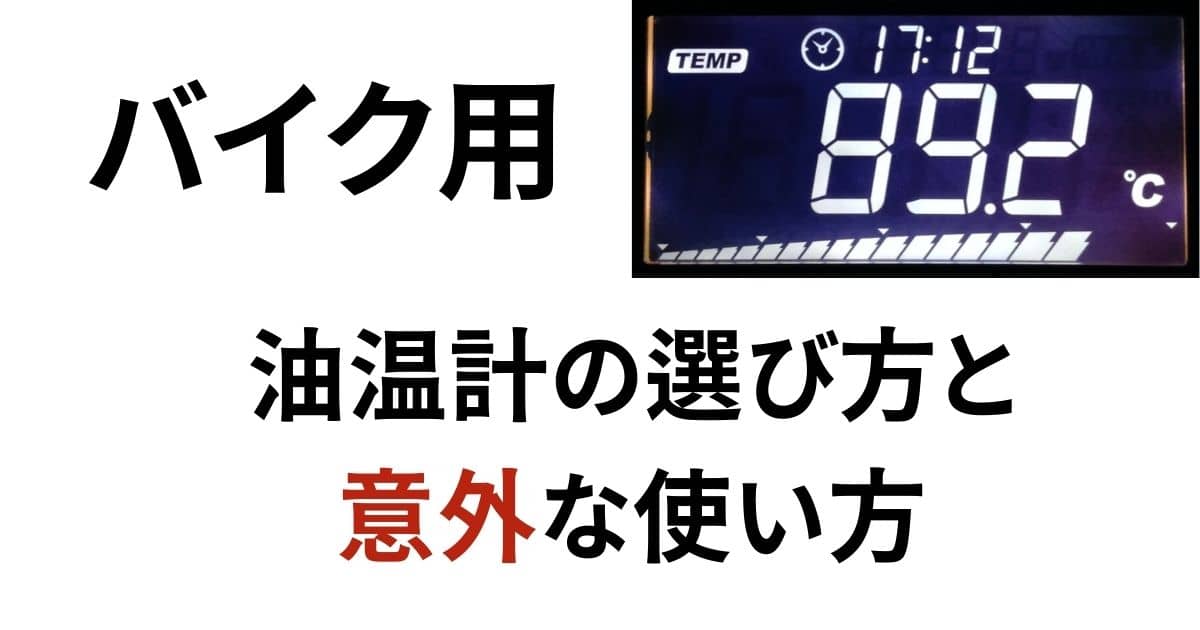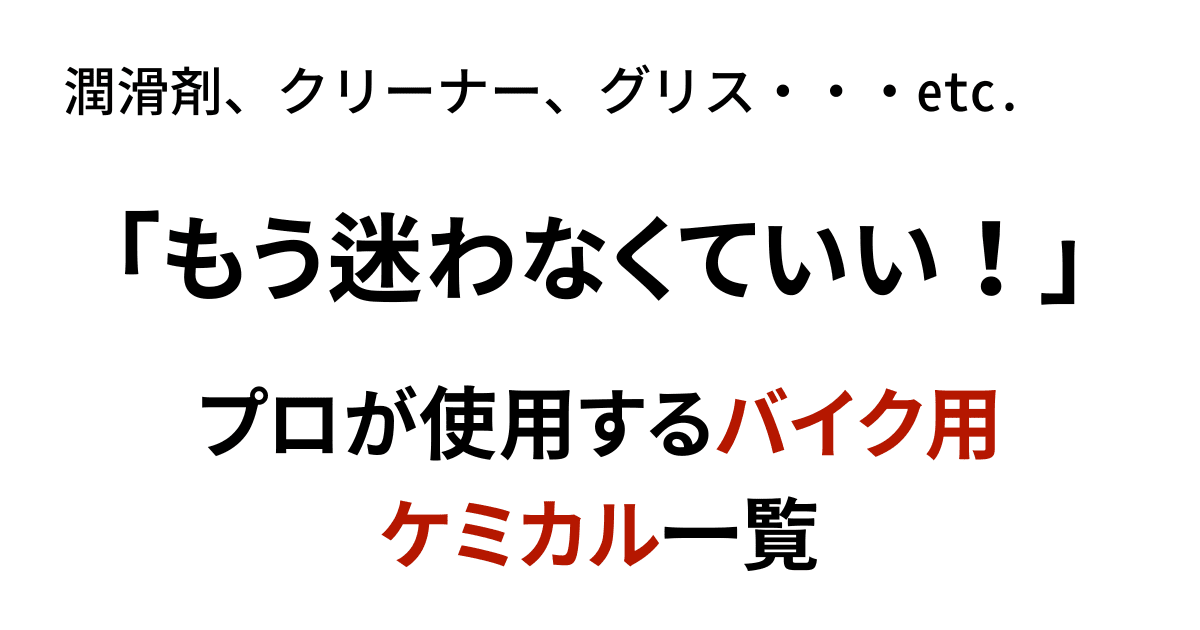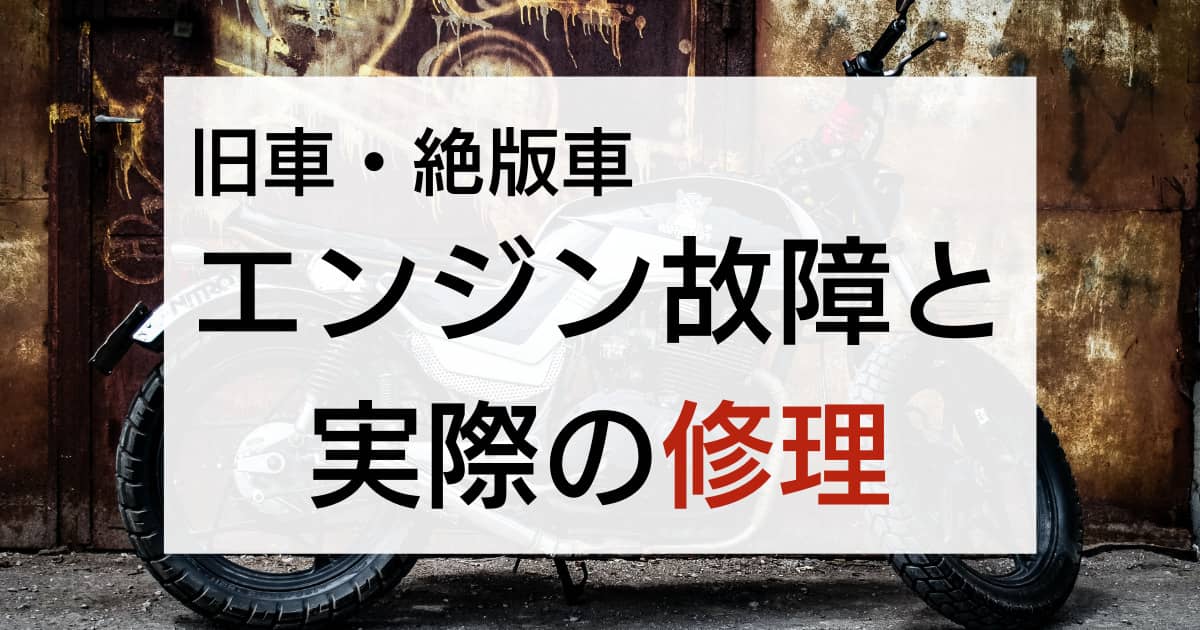プロが教えるエンジンを長持ちさせる方法シリーズ【2】バイクの暖機運転 必要性と具体的なアプローチを紹介
バイクのエンジンオーバーホールを1,080基以上手がけている有限会社ガレージ湘南の日向社長に、4ストの暖機運転について伺いました。
ガレージ湘南は年間、数十基ものエンジン修理をおこなっているエンジンオーバーホールの専門店。
つまり、どうすればエンジンが長持ちするか、どうすればエンジンの寿命が縮むかを熟知しているプロです。
そんな日向社長に伺った内容を、筆者自身が4年間、47,968km実践しました。
2ストの暖機運転についてはこちらの記事を参照してください。
なぜ、暖機運転が必要なのか?
暖機運転をおこたると、最悪の場合エンジンが焼き付きます。
とくに「インジェクション車は暖機運転しなくていい」と考えている人は要注意です。
エンジンが冷えているときは、エンジンオイルも冷えてまだ硬い状態。イメージで例えると、適正油温のオイルが水のようにサラサラなら、冷えている時はドロドロした感じ。

水はなんの抵抗もなくかき混ぜられますが、粘度の高い油だと、抵抗がありますね。
冷えた状態のエンジンオイルがまさにこの状態。
オイルポンプによってエンジン内部にオイルが循環していますが、硬いオイルが抵抗になります。
なので4ストバイクは、エンジンが冷えた状態で始動して(冷間始動またはコールドスタートといいます)、一気に高回転まで回して走った時に、潤滑不良で焼きつきやすいそうです。
油温が上昇することで、オイルがやわらかくなって抵抗が減り、エンジン各部に行き届きやすくなります。
オイルの固さを実感できる方法があります。オイル交換の際、ためしにストローを使って、新しいオイルを吸い込んでみてください。水とちがい、なかなか吸い込めないことが体感できます。
暖機運転でよくある間違い
エンジンをかけて
「すぐ走行できるから暖機運転は必要ない」
「エンジンが暖まらないと走行できないから暖機運転が必要」
という考え方です。
本来、暖機運転で大事なのは、走り出せるかどうかではありません。エンジンが完全に暖まった状態で、適切なクリアランスにすることです。
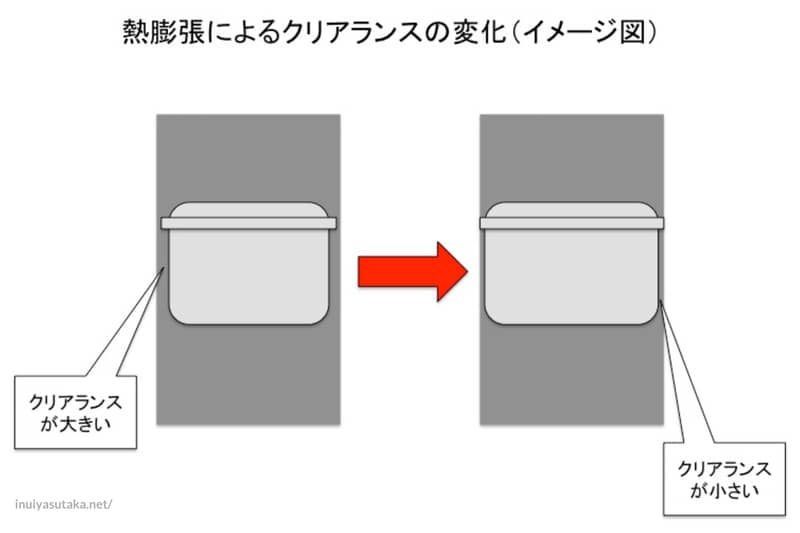
そのために
エンジンオイルの油温を適正な温度にする
というわけです。
たとえインジェクション車でも、冬場にコールドスタート直後で、いきなり高回転までエンジンを回せば、焼き付いたり、エンジンにダメージを与えてしまいます。
(実際、冬場になると、この手のエンジン焼き付きによる修理依頼が増えるそうです)
暖機運転による誤解は、伝える側に原因があると個人的には実感しています。
一般的な暖機運転の解釈
キャブレターを採用しているバイク(または車)はエンジン始動後、エンジンが冷えた状態だとエンストしてしまうため、アクセルを開けるなどしてエンジンを暖める
この一部分だけを切り取って「暖機運転」と伝えた結果、
インジェクションは始動後、すぐ走行可能だから暖機運転不要
誤解している人が多いのだと思います。
言葉の意味や定義をきちんと伝えることは重要ですね。
余談になりますが、始動性だけを切り取って話すと、筆者のCB150T(CB125T 2001年製 4スト空冷二気筒)はキャブ車ですが、真冬でもコールドスタート直後に、走り出せてしまいます。
(「走り出せる」までの暖機時間は5秒以下)
キャブセッティングが濃いからです。
しかし、走り出せるからといって、すぐ高回転までエンジンを回すと、間違いなくエンジン寿命が縮むか、エンジンが壊れてしまいます。
走り出した後、エンジンがしっかり暖まるまで、暖機走行(暖機運転)が必要です。
暖機
weblio辞書
機械を動かし始めた時に、一定の時間だけ負荷の低い運転をすること。暖機運転ともいう。
同じCB125Tでも、年式の古いものはエンジンが暖まるまでに(アイドリングが安定して走行可能な状態なるまで)、時間がかかることがオーナーの間で知られています。
暖機運転が必要な2つの理由
「エンジンオイルが潤滑しやすい状態にする」「エンジンのクリアランスを最適化する」そのために油温が大事。油温を上げる手段が、暖機運転(または暖気走行)という位置づけ。
暖機運転は何分すればいい? 目安は?
多くの方が、暖機運転の時間を知りたいようです。
大事なのは時間ではなく、油温。車種によりますが、適正油温はおおむね80℃から100℃です。
つまりエンジンをかけて、油温が80℃ぐらいになるまでは、エンジンを高回転まで回さず、油温に応じて徐々に回す、という事です。
油温の上昇は、カップラーメンみたいに「3分経ったからOK」、といった画一的なものではありません。
車種や、気温など状況に応じて変わります。
具体的な例を挙げましょう。
CB400SF(キャブ最終型) VS CB125T 油温上昇テスト
https://inuiyasutaka.net/bikeblog/jc06_211027/
冬場、エンジンが完全に冷えた状態でテストを実施。同時にエンジンをスタートさせ、それぞれ油温計で、油温の上がりぐあいをモニタリング。
エンジンスタート後、数十秒で40℃まで上昇するCB400SFに対して、CB125Tは、10℃から20℃まで、なかなか到達しない。
また同じく冬場にCB125Tで、適正油温までの到達時間をテスト。エンジンを始動して暖気後、20℃で走行。油温に合わせて、徐々にエンジンの回転を上げていくと、およそ30分間の走行で75〜80℃に到達。
(外気温が低い場合や、雨天時はそれ以上かかることも)
通年、油温をモニタリングした結論として、CB125Tはオーバーヒートよりも、オーバークールに注意すべきだと思う。
なかなか適正油温まで上がらない=「オイルが冷えて硬い状態の時間が長い」ということ。ついエンジンを高回転まで回したくなっても、(エンジンを長持ちさせることを考えると)グッと我慢しなくてはならない時間も長くなる。
ちなみに水冷の場合、適正水温は70℃から80℃前後です。
次に、どのようなプロセスを経て適正油温にするか?についてお伝えします。
暖機運転のやり方 キャブ車
メーカーの説明書がある場合、それを参考にしてください。
1,必要に応じてチョークを引き、エンジンを始動する

右上にあるレバーがチョークです。めいっぱいまで引いた状態で使用します。
チョークとは
チョーク(Choke)は「塞ぐ」という意味があります。
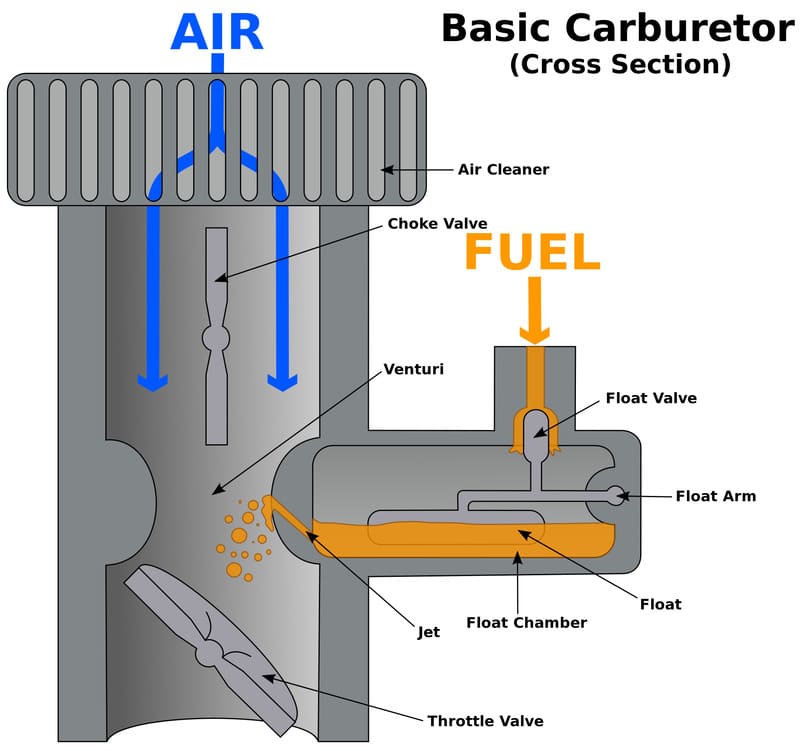
キャブレターは、負圧によって混合気(空気とガソリン)をエンジンに送り込みます。
チョークを使用すると、バルブが閉じて、空気の量を減らし、混合気が濃くなります。
なぜ、チョークを使用するのか?
ガソリンと空気のバランスのことを「空燃比(くうねんひ)」といいます。
基本、キャブレターセッティングで、空燃比はいい具合に調整されています。ただ、空気は気温や気候、標高によって、密度が変化します。
一定ではないんですね。
空気密度と温度の関係
温度が高い=体積が大きくなる(膨張する)=密度が小さくなる=空燃比が濃くなる
温度が低い=体積が小さくなる(膨張する)=密度が大きくなる=空燃比が薄くなる
つまり、秋や冬など気温が低いと、チョークなしでエンジンがかかりにくいのは、薄くなるからです。
チョークを使用することによって、チョークバルブ(弁)で混合気の空気の量を減らし、強制的に濃くしているわけですね。
チョーク使用時の注意点
チョークを使うときは、アクセルを全閉にするのが基本です。
チョーク使用時にアクセルを開けると、(混合気のガソリンに対する)空気量が増えてしまい、チョークの意味がなくなってしまいます。
エンジン始動後も、基本的にチョークを使用している間はアクセルを開けないようにします。
今回紹介したのは、空気の量を強制的に減らすタイプのキャブレターです。
反対に、ガソリンの量を増やして、空燃費を濃くするタイプのキャブレターもあります。このタイプは、チョーク使用時にアクセルを開けると、(混合気のガソリンに対する)ガソリン量が増えて、濃すぎる状態になります。
チョークに対するよくある誤解
手動でチョークを引くバイクは、冷間時「チョークを引いて始動する」ようにつくられています。
(スクーターなど、オートチョークのバイクもあります)
夏場など、気温が高い場合や、エンジンが暖まってる場合を除いて、チョークを引かないとエンジンがかからないのは正常です。
「俺のバイク、チョーク引かなくてもエンジンがかかるんだぜ」
「チョーク引かないと、エンジンがかからないんです」
あたかも、チョークを使ってエンジンを始動することが悪いとか、使わずに始動できると調子がいい、みたいな捉えをされている方がいらっしゃいますが、誤解です。
古いバイク、走行距離を重ねた車両などは、ノーマルであっても新車時と比較して、キャブセッティングが濃くなる傾向があります。
たとえば筆者のCB125Tは、2001年(排ガス規制対応)モデルのため、極端に薄いセッティングになっていました。
8000回転で、エンジンが頭うちするぐらいです。
夏場に納車されましたが、真夏でもチョークを引かないとエンジンがかからない状態でした。
その後、キャブセッティングをやり直すと、正常になりました。さらに走行距離が伸びていくと、だんだん濃くなってきて、最終的に真冬でも、チョークなしで一発始動して、走り出せる状態になっていました。
(CB125Tは冬場、暖機しないと走り出せないことで有名)
つまり、濃すぎる状態になっていたのです。
このように仕様にもよりますが、エンジンの始動性はバイクの状態によって、おおきく左右されます。
2,ゆっくりチョークを戻す
エンジンが始動したら20秒〜30秒ほど待って、ゆっくりチョークを戻します。
「ゆっくり」操作することがポイントです。この時、(回転が落ちてエンストしそうになるなど)バイクの状態によっては、少しずつアクセルを開けてエンジン回転数を上げます。
目安として20秒から30秒としていますが、実際はバイクや、気温によって変わります。
ポイントは、エンジンがかかっても急にチョークを戻さないこと、長々とチョークを引きっぱなしにしないことです。
「エンジンの調子が悪い」と思ったら、原因はチョークの戻し忘れだったという話を、1年に1回は耳にします。
チョークにまつわるトラブル事例
旧車の場合、チョークワイヤーの動作不良で、チョークが引けていない、あるいはチョークを戻しているのに、引いた状態のままになっている(完全に戻りきっていない)というトラブルがあります。
チョークが戻りきらない状態で走行すると、キャブセッティングが濃い症状が出ます。
3,アクセルを開ける
チョークが完全に戻ったのを確認して、ゆっくりアクセル(スロットル)を開けていきます。
まずは上限を〜3,000rpmぐらいまでにして、むやみに空ぶかししないようにします。
アクセルを完全に閉じた状態でエンストしないようなら、ゆっくり走り出します。繰り返しになりますが、急にエンジンを高回転まで回さず、徐々に回転を上げながら走行します。
近隣への騒音対策や、忙しくて時間がない場合、エンジンを始動して、短時間ならアイドリング状態のまま放置する方法もありです。(アイドリング時はチョークを戻します)
ただし、バイクを盗難されないよう、注意してください。
たまに5分〜10分以上、アイドリング状態で放置する人がいますが、ダラダラとエンジンをかけっぱなしにしていると、油圧不足でエンジン(カムシャフト)にダメージを与える要因になります。
状況にもよりますが、北海道や東北など寒冷地をのぞいて、長くて5分から3分ぐらいが限度。
できれば走り出してから、暖機走行したほうがいいです。
信じられない話ですが、世の中には30分以上、アイドリング状態で放置する人(いままでの最長記録は1時間)もいます。ご本人は良かれと思ってやっているのだとおもいますが、逆効果です。
暖機運転のやり方 インジェクション車
始動してすぐ発進できるかと思いますが、徐々にエンジンの回転数を上げるようにして走るのは、キャブ車と同じです。
油温計(または水温計)があればそれを参考にして、なければエンジンが暖まるにつれて少しずつ、回転を上げて走るようにしてください。
長時間、アイドリング状態で放置しないほうがいいのも、キャブ車と同じです。
筆者の場合(冷間時の始動)
最後に、筆者自身がおこなっている暖機の手順を紹介しておきます。

CB150T 空冷4サイクル OHC2気筒 142cc
1,チョークを引いて、エンジンを始動する
2,エンジンの状態を見ながら、ゆっくりチョークを戻す
気温が低い時や、エンジンが完全に冷えている時ほど、必然的にチョークを引いている時間が長くなります。戻しても大丈夫そうだなと思ったら、チョークを戻しながら、少しずつアクセルを開けます。
3,油温(または水温)を見ながら、少しずつアクセルの回転を上げる
1400rpm(アイドリング)→2000、3000、4000という具合に、ミリ単位でアクセルを開けるイメージ。
チョークを戻した状態で、アイドリングのまま放置する、という方法はほとんどやらないです。
4,走りながら暖機する
さきほどお伝えしたように、バイクを停車させた状態で、エンジンを暖機しつづけるのは現実的に、むずかしい面もあるかと思います。
(筆者の場合、単純に気が短いという事もあります)
なので私の場合、停車した状態で暖気運転を続けたり、長々とアイドリング状態で放置することはせず、あるていど暖機したら走り出すようにしています。
冬場、コールドスタート(冷間始動)から、だいたい油温が20℃に達するまでアクセルを開けて暖機運転。
油温が20℃ぐらいになったところで、走り出します。
走り出したあとも、適正油温に達するまで、エンジン回転数は3,000〜4,000rpmぐらいに抑えて走行します。
「私のバイクには油温計がついてません!」
という方は、必要に応じて後付けするか、油温計をつけなくてもいいので、本記事に書かれている事を心がけながら始動・走行するようにしてください。
それだけでもエンジン寿命が変わります。
筆者は70基以上のエンジンオーバーホール現場に立ち会っていますが、暖機運転と同じくらい、定期的なエンジンオイル交換や、オイル選びが大事だと実感しています。
CB1100Rのエンジンスタート
参考までに、コールドスタートで暖機している動画を紹介します。
※暖機運転のデモンストレーション動画ではないので、エンジンスタート後、「アクセルの開け方、開け具合」に注目してください。
47,968km暖機運転を続けた結果
ここまでお伝えした内容を、筆者自身が4年間、自分のバイクで実際に試してみました。
(90%以上の精度でオールシーズン取り組みました)
47,968kmテスト走行した結果、おどろくべき検証結果が出ました。詳細は以下の記事に掲載しています。
ご自身の目で確かめてください。